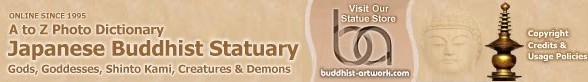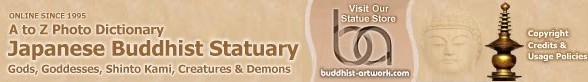|
| 一名麝香童子ともいい、その本地は釈迦如 |
| 来とされます。童子角髪の結髪に袍を着て立 |
| 位で侍し、右手に宝珠を持ち、左手に鑰(鍵 |
| )を持ちます。この童子が宝珠と鑰を持つの |
| は、弁才天が人々の願いを叶える時、その受 |
| け渡しを勤める役です。 | | |
|
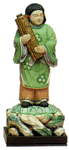 |
| またの名を赤音童子といい、本地は普賢菩 |
| 薩です。帯を両手に抱えて捧げ持つポーズを |
| とります。印相は金剛合掌印です。 | | |
 |
| 一名香精童子ともいい、本地は金剛手菩薩 |
| です。右手に筆、左手に硯を持ちます。弁才 |
| 天は学問の神でもありますから、学問・弁舌 |
| ・叡知などの向上を願う人のために、弁才天 |
| が功徳を示すときに、この童子が功徳の取次 |
| ぎをする役です。 | | |
 |
| またの名を召請童子といい、本地は薬師如 |
| 来です。両手に秤の入った箱を捧げ持ちます。 |
| 弁才天が、金銀財宝の願いを叶えてくださる |
| 時、財宝を計る役す。分に応じた功徳を与え |
| るために秤が必要です。 | | |
 |
| またの名を大神童子といい、本地は文珠菩 |
| 薩。左肩に稲束を担いで、右手に宝珠を持ち |
| ます。弁才天と稲荷神が習合しましたので、 |
| 稲荷神の功徳を稲籾童子に表現したものでし |
| ょう。 | | |
 |
| 一に悪女童子というが、この場合の悪は善 |
| 悪の悪ではなく、強いという意味でしょう。 |
| 本地は地蔵菩薩です。計升は穀類の量目をは |
| かる升(ます)のことですから、五穀豊穣で |
| 収穫多きを願う人々に、分け与える役です。 | | |
 |
| またの名を質月童子といい、本地は栴檀光 |
| 仏。頭上に飯櫃を乗せて右手でこれを支え、 |
| 左手は拳として腰に当てています。炊いた飯 |
| まで用意する係りがあります。 | | |
 |
| またの名を除咽童子といい、本地は摩利支 |
| 天です。両手で衣裳を捧げて持ちます。 |
| 美服を与える係りです。 | | |
 |
| 一に悲満童子ともいい、本地は勢至菩薩で |
| す。両手に蚕を入れた器を捧げて持ちます。 |
| これは養蚕農家の人々に限らず繊維に係わる |
| 人々の願いをかなえる係りです。 | | |
 |
| 一に密跡童子ともいい、本地は無量寿菩薩 |
| です。前に酒甕を置き、右手に杓柄を持って |
| 、左手には宝珠を持っています。本地が無量 |
| 寿菩薩だけあって、酒は美味百薬の長であり |
| 、左手に何事も意のごとく叶えられる霊力を |
| 示す宝珠を持ちます。 | | |
 |
| 一に旋願童子といい、本地は観世音菩薩で |
| す。右手に矢と左手に弓を持ちます。人にふ |
| りかかる災悪の魔を退治する役でもあり、キ |
| ュウピットのように人の心を射止める弓矢で |
| す。 | | |
 |
| 一に臍虚童子といい、本地は弥勒菩薩です |
| 。右手に不動明王のように剣を立てて持ち、 |
| 左手は胸前で宝珠を捧げ持ちます。煩悩を払 |
| い、悪魔を遠ざけ、願いを叶えて下さいます |
| 。 | | |
 |
| 一に施無畏童子ともいい、本地は龍樹菩薩 |
| です。宝珠を盤に捧げて両手で持ちます。 |
| 如意宝珠は何でも意のごとく願いや望みが叶 |
| う有難い珠ですから、本来は一つでよいので |
| すが、弁才天のまわりには多くの宝珠が用意 |
| されています。仏神には宝珠を持つものはい |
| くつかありますが、弁才天ほど身のまわりに |
| 多くの宝珠を有している神は他にはありませ |
| ん。 | | |
 |
| このほかに善財童子を加えて十六童子とす |
| ることがありますが、これは一名乙護童子と |
| いって、袋の口を右手で握って持ちます。 |
| 金福を願う者に分け与える係りです。 | | |
|
|

|
| 一に随令童子ともいって、本地は薬王菩薩です。 |
| 牛や馬を索いて立ちます。博労のような係りです。 | | |
|
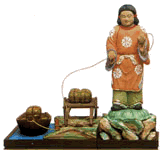
|
| 一に光明童子ともいい、本地は薬上菩薩です。 |
| 右手で川舟と荷車の綱を索いて持ち、左手に宝珠を |
| 捧げて持ちます。そうした商売にたずさわる人々の |
| 願いを叶えて下さるために、この係りもあります。 | | |
|
| 以上一ヶ月を二交代で給仕する十五童子をそろえて、人々の願いを叶えて下さる弁才天の功徳を示すために、 |
| 弁才天の回りに囲続しています。 | |